*REVIEW_Music 2
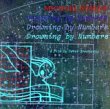 『Drowning
By Numbers』 Michael Nyman
『Drowning
By Numbers』 Michael Nyman
☆☆☆☆
「数に溺れて」
マイケル・ナイマンの数あるサントラアルバムの中で、最も素晴らしい1枚(『ピアノレッスン』や『ワンダーランド』もいいが)。完全にP・グリーナウェイの映画を凌駕している独立したサウンドトラック。サウンドトラックというより、現代的美しさを極めた音楽アルバムそのもの。1曲目は、モーツアルトの「シンフォニア・コンチェルト」のスロー・パッセージをナイマン流にアレンジした弦楽曲。弾むように明るい曲調の3曲目、8曲目。タイトル曲『ドローイング・バイ・ナンバー2』では、音楽が空間で結晶しているようだ。静かな吐息のように管楽器が旋律を奏で、弦の音が乗ってくる。低音部が加わりリズムが刻まれ、ヴァイオリンがミニマムミュージック的な旋律を反復する。ナイマンミュージックの至福の瞬間。ラストの3曲メドレーは、これぞマイケル・ナイマンという感じでたたみかけていく。聴いていると音楽美の中に陶酔してしまう。時折ナイマンCDは、録音がよくないことがあるが、これは音の分離も明快で鮮明。ジャケットも知的(裏面も)。中面にはナイマンのエッセイが掲載されている。まさに完璧な1枚。
*************
 『OLD
BOY』 Sound Track
『OLD
BOY』 Sound Track
☆☆☆☆
「オールドボーイ」
ビルの屋上から飛び降り自殺しようとしている男のネクタイをわしづかみにする主人公。
自殺男は問う。「あんたは誰だ?」
男は言う。「俺は、俺は・・・」
この科白から始まるサントラ。1曲目はこのシーンに流れる曲で、
次が雨降る公衆電話前で拉致される男のシーン。
ラストは、アラン・ドロンの「太陽がいっぱい」を思わせるワルツで終わる。
サントラでは、このワルツの最後に、誘拐犯のハミングが入っていて、 フェイドアウトして消えていく。
映画の中にこの部分はない。
サントラの内部で、映画が音楽的に再構成されている。
韓国輸入盤は、例の紫色のハンカチのモチーフが表紙。
16Pのカラーブックレットが入っている。 デザインは韓国色が強い。
*************
 Glenn
Gould『Beethoven Piano Sonatas Op31 Complete』
Glenn
Gould『Beethoven Piano Sonatas Op31 Complete』
☆☆☆☆
「テンペストー嵐」
ハイドンの後期ソナタも、ブラームスもいいが、このCD(2枚目)におさめられているベートーベンピアノソナタの「16」「17」「18」(作品31-1、2、3)はとてもいい。
「16」の出だし、彼独特の玉が転がっていくようなタッチと、音質、速度感が見事だし、気持ちがいい。「17」はテンペストとして有名な楽曲だけれど、多くのテンペスト演奏の中でも、彼のこの演奏はもっとも聴きやすく、何度でも聴ける、優れたものだ。
ベートーベンのピアノソナタ弾きとしては、グルダがベストだと思っているが、グールドのこれも、違った意味で最上のもののひとつ。
長調、短調、長調という曲の流れも、明るく始まり、テンペストを味わって、朗らかな「17」で終わるので、心地よく聴いていける。たぶんグールドもこのことを意識して、この3つのソナタを分離せずに1枚に入れたのだろう(最初のアナログ盤でもそうなっていた)。3つのソナタの9つの楽章は、どれも味わい深く、現代的で、輝いている。ジャケットワークも素晴らしい。ただ、グールドの場合、名盤がなぜか発売されなく(絶版に)なってしまう傾向がある。モーツァルト・ピアノソナタ全曲集の2枚組CDも、今や手に入れるのは非常に困難。
*************
 浜田真理子「MARIKO」
浜田真理子「MARIKO」
☆☆☆☆
「孤高..美しい..切ない..」
このアルバムが、渋谷のタワーレコードの店内で流れていた。それが出会いだったと思う。1曲目、ピアノ弾き語り。この声、歌、トーン。なんと言ったらいいのか。彼女の歌は、通して何曲も聴くものではない、2、3曲聴くと、もういっぱいになってしまう。彼女の個人的なメ何かモがこちらに伝わってきて、いっぱいになってしまう。シンプルな録音が、彼女のボーカルとピアノを際立たせている。
3曲目「残されし者のうた」。この曲と歌の前では、言葉は敗北してしまう。形容することができません。キャロル・キングとか、カーラ・ボノフとか、彼女の音楽のルーツにアメリカの女性シンガーソングライターたちがいるのだろうが、彼女はたった独りで、自分の場所に、自分の音楽と一緒に、立っている。
*************
 SOPHIE
ZELMANI 『SOPHIE ZELMANI』
SOPHIE
ZELMANI 『SOPHIE ZELMANI』
☆☆☆☆
「草原を渡る風。独りで立っている女性。切なくて、優しい歌」
アコースティックなピアノとギターが中心になった素朴なサウンド。その響きに、彼女ならではのかすれた、フォーキーな、ガーリー・ボーカルが乗ってくる。草原の緑や、青空や、ゆっくりと動いていく雲を連想する。でもそれだけではない。ただ明るく素朴なだけではない。それは、自分にも他者にも媚びることのない、彼女のソングライティングと、歌声からまっすぐに伝わってくる。切実さ、正直さ、誠実さ、それらを北欧の女性アーチストたち(スウェーデンの彼女、ノルウェーのレネ・マーリンなど)は共通の資質として持っている。だから彼女たちは悲痛なことを歌っても、どこか日差しが差しているような楽曲になる。その光はカリフォルニアや地中海のようなものではなく、北の、寒い曇り空をベースにしたもので、だからこそ澄んだ、透明なものになる。
彼女のアルバムジャケットは、中身の音楽を性格に反映している。このアルバムでは、素朴な表情で笑っているソフィーが、次の『プレシャス・バーデン』ではまったく様変わりして、渋い大人の表情になる。音楽もためらうことなく深まりを見せる。自分が自分であることと向き合い、それを音楽で表現していく。そういうタイプのミュージシャンがここにいて、魅力的な歌がある。
*************